
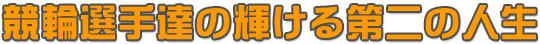
当時、競輪は絶頂期で同年2月の一宮ダービー(優勝=工藤元司郎・写真左)、11月の岸和田ダービー(優勝=荒川秀之助・写真右=決勝戦進出選手の紹介場面)をはじめ、どこの競輪場も超満員のファンが詰めかけ熱気であふれていた。
 |
 |
勤務していた新聞社のデスクに高知行きを命じられたのはそんな時期だったが、岡山から高知に向かう「土讃線」(どさんせん)で現地に着くまで、この取材旅行が私自身の人生を変えることになろうとは夢にも思わなかった。
瀬戸大橋が完成(1988・昭和63年)する前のことなのでかなり時間はかかったが、四国山脈を越え、高知駅の10㌔ほど手前の「御免」(ごめん)という駅で下車。右手に見える小山の上に建つ施設に到着した(写真左)。これが、41歳になる山崎選手(同右)と祥子夫人が中心になって築いた障害児のための新しい療養施設「土佐希望の家」だった。
同選手は、1928(昭和3)年に高知県で生まれ、若いころは自転車店で働き、高知競輪の創設時(1950・昭和25年)にプロ入り。3年後には全国1を決めるダービーの決勝戦で中井光雄に続く2着(松本勝明、山本清治、白鳥伸雄=ともに日本名輪会員らに先着)になり、その脚力が高く評価された。
一方、家庭面では1963(昭和38)年8月に生まれた3人目の子・昇が重度の脳性まひに見舞われ、食事や大小便はもとより寝返りもできない状態で山崎は毎日悩み続けた。
その結果、家庭では十分な手当てができないと思い、昇を連れて県内の病院や施設を回り、東京の小児病院へも入院させた。そのあわただしさの中で、「障害児家庭はどのくらいあるのか」調べたところ、高知市内に70軒、高知県内には300軒の家族があることを知った。
驚いた山崎は市内の70軒の大半を訪ね、悲壮な状況を把握したあと、「昇を東京の病院から連れて帰り、家内の実家に“希望の家”というのをつくり、私たち夫婦と、私の母、家内の母で数人の子を預かることにした」と言う。これには相当の費用がかかっただろうが、競輪で得た賞金(収入)の大半を注いだとのことである。
瀬戸大橋が完成(1988・昭和63年)する前のことなのでかなり時間はかかったが、四国山脈を越え、高知駅の10㌔ほど手前の「御免」(ごめん)という駅で下車。右手に見える小山の上に建つ施設に到着した(写真左)。これが、41歳になる山崎選手(同右)と祥子夫人が中心になって築いた障害児のための新しい療養施設「土佐希望の家」だった。
 |
 |
一方、家庭面では1963(昭和38)年8月に生まれた3人目の子・昇が重度の脳性まひに見舞われ、食事や大小便はもとより寝返りもできない状態で山崎は毎日悩み続けた。
その結果、家庭では十分な手当てができないと思い、昇を連れて県内の病院や施設を回り、東京の小児病院へも入院させた。そのあわただしさの中で、「障害児家庭はどのくらいあるのか」調べたところ、高知市内に70軒、高知県内には300軒の家族があることを知った。
驚いた山崎は市内の70軒の大半を訪ね、悲壮な状況を把握したあと、「昇を東京の病院から連れて帰り、家内の実家に“希望の家”というのをつくり、私たち夫婦と、私の母、家内の母で数人の子を預かることにした」と言う。これには相当の費用がかかっただろうが、競輪で得た賞金(収入)の大半を注いだとのことである。

しかし、その過程で悲劇が起きた。昇が1967(昭和42)年に3歳半で短い生涯を閉じたのだ。山崎夫妻は「何もしてやれなかった」ことを詫び、霊前に泣き伏したまま動かず、今後も福祉活動を続けることで菩提を弔う決意を固めた。
これに呼応したのが同郷の松村憲(第4回高松宮記念杯の覇者)で、直ちに日本競輪選手会に呼び掛け、「財団法人高知県重症心身障害児・者を考える会」も大きな力を発揮。高知県が拠出した1千万円、高知市の200万円、周辺の市町村からも180万円が寄せられるなど「土佐希望の家」の建設は着実に進んだ。
さらに、「ファンが買ってくださる車券代金を有効に使い、社会福祉や機械産業の振興に貢献することが競輪の使命」という「日本自転車振興会」(現JKA)も多額の援助金を用意し、ついに上記のような立派な施設が完成。山崎は施設の理事長と競輪選手の両道を驀進した。
 |
 |
 |
それから何10年かの歳月が過ぎ、大災害を想定して「土佐希望の家」は安全な場所に移転。それとは別に宿毛市(すくもし)にも施設が完成するなど「昇の菩提を弔う事業」は進み、山崎は1986(昭和61)年に選手生活から引退。希望の家の理事長職も退き(現在は顧問)、84歳になった今では、山崎と松村の栄光を称えて創設された「山崎勲杯」と「松村憲杯」を楽しみにしているという。
参考までに数年前に撮影した山崎勲(写真中央)と「山崎勲杯」(写真右)の写真を掲載したが、このにこやかな笑顔の中に「昇も喜んでくれているだろう」という満足感と大事業を成し遂げた男の魅力が漂っているように見えた。

 |
 |
「土佐希望の家」の話題はひとまず終了するが、この原稿を書きながら「面白い年齢」に気付き、改めて付け加えたくなった。というのは、希望の家が完成した時、山崎勲は41歳だった。ところが、別な所に41歳で第2の人生を歩みだした者がいる。2008年(平成20)年に現役を退いた59期生の菅原克己(兵庫=写真左)がその人だ。
スポーツ選手の引退時期は難しく、競輪も例外ではない。昔は68歳まで戦った湯浅昭一(群馬)や、66歳で引退した萩原三郎(静岡)、金子唯夫(長野・後に神奈川に移動)、黄金井光良(埼玉)といった選手もいたが、現在は30代で引退する選手も少なくない。
菅原も迷ったが、21年間の現役生活の後、2008年3月31日に引退した。前述のように41歳の時だが、以後の向上心が素晴らしい。彼はその翌日、看護師を目指して兵庫県内の「明石市准看護高等専修学校」に入学。2年間の教育を受けた後、今度は「神戸医師会看護専門学校」で3年間、血のにじむような指導を受け、今年の春、遂に看護師の資格を手にして実務に就いているようだ。
右の写真は、専修学校で1年目の課程を終えた生徒に「戴帽式(たいぼうしき)という厳かな儀式が行われ、2年目を迎えた菅原は式の手伝いをしていたが、初めて撮影した私には感動的なシーンだった。
ついでながら、競輪選手のOBで看護師になったのは、岡山の出宮政幸(23期生)、兵庫の閑谷隆(63期生)に次いで菅原が3人目と聞いたが、菅原は「生死の境をさまよっておられる重症の患者さんに、ぜひ、生き延びてください」と願いながら看護を続けているそうだ。
福祉活動に生涯をかけた山崎勲と、患者の生死の狭間(はざま)で懸命に働く菅原。この2人を紹介して今回は終わらせていただく。
筆者の略歴 井上和巳 昭和10年(1935)年7月生まれ 大阪市出身 77歳 同32(1957)年 デイリースポーツに速記者として入社 同40(1965)年から競輪を担当 以後、定年後も含めて45年間、競輪の記事を執筆 その間、旧中国自転車競技会30年史、旧近畿自転車競技会45年史、JKA発行の「月刊競輪」には井川知久などのペンネームで書き、平成14(2002)年、西宮・甲子園競輪の撤退時には住民監査請求をした。